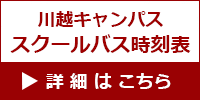第9回東邦ピアノセミナー報告

第9回東邦ピアノセミナーが去る7月26日(日)に文京キャンパスで行われました。今回の講座テーマと講師の先生は次のとおりでした。
- ●講座1:「時代様式に基づいたピアノ演奏とは─9」〜19世紀のピアノとピアノ音楽〜
- 講師:中島裕紀先生
- ●講座2:「子どものためのピアノ教本研究〜ドイツ・オーストリアの教本を題材に〜」
- 講師:浦川玲子先生
- ●講座3:「ドビュッシーのピアニズム」〜現代音楽の始まり〜
- 講師:井上淳司先生
講座終了後に、ピアノ専攻主任教授の大場文惠先生の司会で、3人の講師の先生方に「セミナーの報告座談会」を行っていただきました。その模様をお伝えします。
■講座1:「時代様式に基づいたピアノ演奏とは─9」〜19世紀のピアノとピアノ音楽〜
- 大場:
- 先生方、今日は講座を担当していただきましてどうもありがとうございました。レッスンがあったため講座3は聴けませんでしたが、講座1、2とも、参加された方たちは大変熱心にお聴きになっていらしたように感じられました。
それでは中島先生から、講座1について、どういった経緯でこのテーマを選ばれたのかお伺いしましょう。 - 中島:
- 今回スポットを当てました19世紀は、楽器としてのピアノとピアノ音楽の興隆期で、私を含むピアノに携わる人間にとりまして、宝の山のような興味深い時代ですが、第8回までの講座では、まだあまり詳しく触れられていない部分もありましたので、もっと掘り下げていったら面白いだろうと思い、このテーマを選びました。
- 大場:
- 本当に19世紀というのは、ピアノにとっては一番豊かな時代と言ってもいいくらいの時代ですよね。
- 中島:
- そうですね。そして、ピアノばかりではなく、社会や産業、思想などが変化したまさに激動の時でしたから……。
- 大場:
- 先生が社会状況からお入りになったので、本当にそれがよく分かりました。やはり社会の変化が大きく作用していますね。
- 中島:
- 芸術の世界は、社会の流れと隔絶されている訳ではなく、社会的な状況や思想的なムーブメント、さらには経済などと密接な関係があって、その絡みの中から、例えば個人主義やロマン主義、感情の表現なども生まれています。
- 大場:
- そしてまた例えば産業革命ですとか、それに加えてピアノがどんどん変遷していったという、そこが大きく関わっていますね。
- 中島:
- 時代というのは偶然のような必然から出来てくるのですが、今考えてもワクワクしてしまうような時代だったのではないかなと思います。
- 大場:
- 先生はこの講座をなさるに当たって、きっとまた研究を深められたと思いますが、如何でしたか?
- 中島:
- 普段のレッスンではこういう話もしていますが、実際に講座用にまとめてみますと、もっと知りたい、話したいという気持ちが尽きず、その作業がとても楽しかったです。でも講座は90分という限りがあるものですから、その折り合いが難しいところでした。19世紀は講座を終えた今、益々面白い時代だと思っていますし、今回触れられなかった部分にも、宝がたくさんありますので、是非これを機会に皆さんでその先を更に深めていただけたらと思います。
- 大場:
- そうですね。本当に何回かのシリーズにしていただいてもいいような内容のものだったと思います。
受講者の反応をお感じになりましたか?
- 中島:
- 受講者の皆さんは、「学ぼう」という気持ちでいらしていますから、その熱が私にも伝わってきました。皆さんのお顔を拝見しながらお話しさせていただくと、熱心にメモをされたり、頷きながらお聴き下さったりと、よい反応があり、私自身も話に熱が入って、とても楽しく進めることができました。
ピアノの変遷のお話もなさいましたが、ベートーヴェンを筆頭に、ピアノの発達によって作曲家もそれに合わせて作品を書いていったと思いますが、それも19世紀の音楽の特色の一つと言えるでしょうか?
- 中島:
- 特にベートーヴェンの時代は、ピアノの構造原理が完成したとは言え、音域はどんどん広がり、楽器の機能も発達していく途上段階でしたので、講座で例を挙げましたように、ベートーヴェンはその機能を実験的に表現に使っていた面もあります。例えば、限られた音域で、表現するための音使いや転調もそうですし、以前の楽器ではできなかったsfやデュナーミクの可能性を極限と言えるほど追求し、そこに感情の表現を見出そうとしていたこともその一つです。ロマン派の作曲家の頃になると、機能の充実と共にピアノの楽器としてのイメージがある程度定まり、機能面の可能性を強調するよりも、ピアノという楽器から表現の可能性を追究していくという意識に変わっていきます。勿論、リストなどによって耐久性が要求された面もありますが……。
日頃のレッスンで、そうしたところまで生徒さんに伝えたりなさるのですか?
- 中島:
- 楽曲の成り立ちや時代的なイメージを広げさせるために、「この作品の時のピアノはこういう状態だった」というようなことをよく話題にします。
ピアノを演奏したり学んだりしている方で、「弾く」ということは一所懸命するものの、ピアノは指を動かす練習道具のように思ってしまっている場合もあります。ですから今回の講座では、もっと楽器に対して愛情と興味を持っていただく機会にしていただけたらと思って、楽器の特徴などにも触れました。
今日のお話は、現役の学生さんにも聴いていただきたい内容だったと思います。
- 中島:
- そうですね。この内容を学生向けにも大学でお話しできるチャンスがあればと思います。
講座2:「子どものためのピアノ教本研究〜ドイツ・オーストリアの教本を題材に〜」
- 大場:
- 浦川先生は一つの教材に絞って説明していただきましたが、この教材を選ばれた理由は?
- 浦川:
- これはウィーンの子どもたちが一番よく使う教材の一つで、ウィーンの大学の教育学部のピアノ指導法の授業でもこれをよく取り扱っています。それと、本学にはウィーンにアカデミーがあって、ウィーンとは密接な関係がありますので、やはりウィーンのものを紹介したかったのです。それでこの「ペーター・ハイルブート」にしました。
- 大場:
- この教材が特に優れている点は、どのような所でしょうか?
- 浦川:
- これは入門用ですが、1冊の中に必要なことがすべて詰まっています。
今日は受講生の方にすごく喜んでいただけたのが、この中に載っているテクニックについての課題でした。これは、動物を例えに出して指のテクニックを上手く説明して学ぶというものです。最初に出てくるのは動物ではなくて、水が指先から滴り落ちるような水滴のポジションなのですが、そこから始まって、それがずっと関わっていきます。そういったテクニックを最初の段階から分かり易く説明しているというところが、この教材の優れたところだと思います。 - 大場:
- テクニックはとても大切なことなので、教材の中から自然に身に付いていくというのは素晴らしいですね。
テクニックに関しては、教材の最後の方で指をくぐらせる所がありますが、あれはピアノにとってはとても難しいテクニックですね。それがもうこの入門段階で出て来るというのは、本当にいいことだなと思いました。 - 浦川:
- この教本では親指を支柱のように使って橋渡しをするように書かれています。これは教える側も丁寧に説明しないといけませんね。
――――この教本では、黒鍵から始まったり、早くに両手が交差したりなど、日本で普通に行われている教育とは随分違いますね。
- 浦川:
- 最初の段階から読譜とか作曲とか暗譜とか理論的なこととか、動きのことも含めていろいろなことを満遍なくやっていた方がいい、という考えが根底にあります。
作曲家のお立場から、井上先生はこういう教本はどうお感じになります?
- 井上:
- ドイツ・オーストリアのこういう教材を見るとかなり自由な印象を持ちます。この教材でも例えばグランドピアノの内部奏法が載っていますが、日本でこんなことをしたらまず嫌がります。だから日本は明治時代に西洋音楽をどこか間違った形で取り入れて、以来ずっとその形で来ているので、なかなかそういうのが考え方として浸透しないのではないでしょうか。
中島先生はいかがですか?
- 中島:
- 以前、ドイツで子どもたちを教えている音楽学校の先生に、ドイツのピアノ導入教材についてお尋ねしましたら、紹介してくださったドイツの教材がやはり今日のようなアプローチの仕方で入っていくものでした。こういうものをどんどん取り入れていくことは、教育の可能性が広がることと思います。
- 大場:
- 今日の講座を伺っていまして、楽器を楽しんだり音を楽しんだりという、「楽しむ」ということが前提にあるように思いました。日本では「楽しむ」というところが少し足りないのかなという感じがします。
- 中島:
- すぐに結果を求めてしまうのでしょうね。子供の教育で、結果を性急に求めてしまってはいけません。先程のドイツの教材でも、音を鳴らしながら楽しむものがたくさんありましたが、それをどのくらいやるのか訊きましたら、子どもが満足するまでやらせてから次の段階へ進む、と仰っていました。
- 浦川:
- 音楽の本質的なところをピアノを通して学ぶことがとても大事で、この教本にはそういうエッセンスがいっぱい詰まっていると思います。
- 中島:
- 逆に今はそういう方向に戻していかないと、日本では、ピアノを学ぶということに歪みが生じてしまっている面もあります。この20年間の日本の子どもたちの技術の向上は目覚ましいものがあります。しかし、その反面、もしかしたら本質的なものが失われているのではないかと思われる側面もあります。
- 浦川:
- グレードの高い曲が弾けるとか指が速く動くとか、そういう方にどうしても目がいってしまいますね。
- 中島:
- 是非これを翻訳・出版して、全国で講演などをなさっていただきたい。
- 大場:
- 先程もお話が出ていましたが、内部奏法がこの教本に出てくるのが驚きました。内部奏法をすれば必ずピアノの中を覗きますよね。でもピアノの蓋を開けたことがない、どうやって音が出ているか分からない、という人が音大生でも結構います。楽器のことは調律師任せ、自分は弾く人、のような感覚なのでしょうか。小さいうちからピアノの中を見て、音がどうやって出てくるか、そういったことまで知ることは本当に素晴らしいと思います。
- 浦川:
- アンサンブルもそうですし、鍵盤を使って行ういろいろな遊びは、人がやっていないようなことをやるという自由な想像力に結び付いていきますし、子どもたちはとても楽しんでやります。そういう機会を与えてあげるのが我々の役目ではないでしょうか。
レッスンで子どもが体を動かしたり自由に歌ったりするなどしてエネルギーを発散し、またそこからインスピレーションを得ているのかなと感じます。いろいろな楽器を使ったりしてレッスンをしていくのもいいことだと、常々思っています。この教本ではそういうことができますね。
これはやはり翻訳・出版がなされるといいですね。
■講座3:「ドビュッシーのピアニズム」〜現代音楽の始まり〜
- 大場:
- 井上先生、今日はピアノのセミナーですのに、ゲスト出演をお願いいたしました。ありがとうございました。
ドビュッシーを取り上げられた理由をお聞かせください。 - 井上:
- 前回遠山菜穂美先生がフォーレでしたので、その流れからいけばドビュッシーかなと思いまして、テーマにしました。以前、青柳いづみこさんの本を読んで、日本人のドビュッシー観がちょっと違っているというのを覚えていまして、ではそれを今度は自分で検証してみようかなというところから始まりました。ですから受け売り的な所もありますが(笑)、一応自分の体験も含めてお話ししました。
- 大場:
- 先生は時代的なことにも触れられたりなさったのですか?
- 井上:
- 当時、詩人や小説家、画家などいろいろな芸術家が集まって来るサロンにドビュッシーも出入りし、彼らと交流し、交友関係がかなりありました。その辺りから入りまして、ドビュッシーは絵が好きだということでそこに絞って、画家たちとの関係を説明し、ドビュッシーの志向を探るということで、「メロディー」と「ハーモニー」と「リズム」という音楽の三要素の観点から、ドビュッシーの好み、あるいは作曲上の志向を探るというところを主旨としました。
- 大場:
- やはり作曲家の視点と、私たちピアノの視点とは違いますね。
- 井上:
- そうですね。自分でも曲を書いていますので、ドビュッシーが何を考えているのか、とても僕なんかのレベルの作曲家では追いつかないところもあります。ですが、やはり分かるところもありますし、どういうところにヒントを得ているかということも分かります。
一般に印象派とされるドビュッシーが好きだった絵はベラスケスやモロー、ドニなどで、必ずしも印象主義ではなく、彼の音楽の一般的なイメージとはやや違います。先生はどのようにお感じになりますか?
- 井上:
- きれいに弾きすぎるのではないでしょうか。皆さんそう思っているのですが、実は「きれい」の裏側には「きたない」があるという、そこを感じなければ。何がきれいか、表面的なところだけで捉えてしまったら、ドビュッシーではなくなってしまうのではないでしょうか。
そのまま出すというのは、やはり無粋なんでしょうね。それは言うならばチラリズムのようなもので、もろに出すのではなく、ちょっと誘ってというような、裏側をチラッと見るという、その辺りのところを演奏の中に入れられれば、それはドビュッシーに通じたと言えるかなと思います。
きれいなだけの音楽だったら、やはり残らないだろうと思います。100年以上経って未だに魅力的であるというのは、やはりその裏側にそういう影の部分があるというのと、最後にご紹介した、ブーレーズが言った「どんなものにも屈折しない」というところでしょう。その辺りが天才的ではあるのでしょうけれど、やはり裏を知っているからこそのドビュッシーだから、長い間多くの人に愛されているのでしょう。表の明るい部分だけではないという、そこがピアニストに望むところでもあるかも知れません。
ドビュッシーはエラールのピアノをよく使っていたそうですが、エラールはまだ弦が平行に張られていて、声部がクリアーに聴こえてきます。そういうピアノで曲を書いていたということと、ガムラン音楽に影響を受けたりしたことと、何かリンクするものはあるのでしょうか?
- 井上:
- 素材としてはそういうものに興味はあるけれど、それを超えたところで書いていたのでしょう。ガムラン音楽をそのまま出すのだったら、ガムランの楽器を使えばいいのだし、全音音階で書きたければ全部そうすればいいのだけれど、ドビュッシーにとってはそれが目的ではないということです。要するにピアノの響きの何かを彼は知っていて、それを音符に落として楽譜にする、その作業のおかずみたいなものとしてあるわけで、それがメインディッシュにはなっていないということだと思います。エラールのピアノを私は使ったことがないので、どういう響きをするかは分かりません。
- 中島:
- ベヒシュタインも好んで使っていたそうですね。古い設計のベヒシュタインは、ペダルを多用しても音がきれいに立ち上がりますから、私もドビュッシーの曲を弾いてみて、基音と倍音の調合がとても不思議で、面白く感じた経験があります。
- 井上:
- ドビュッシーは耳がかなり良かったので、高次倍音までも聴き取れて、それを微妙なタッチで出すわけです。だからソルフェージュ能力が低い人は苦労するわけですよね。ドビュッシーの求めた響きは、ドビュッシーの耳でしか捉えられなかったところがあるのかも知れませんね。
- 大場:
- 日本人の多くはフランス音楽について、水彩画とか淡い感じを印象として持っていますが、それは間違いだと私の友人である海老彰子さんは言っています。彼女がフランスでペルルミュテールに初めてレッスンを受けた時に、何でそんな弾き方をするんだ、そんなさっぱりなんて弾いてはダメだ、もっとしっかりと弾きなさい、自分はラヴェルからもそう習っている、と言われたそうです。印象派の音楽というと、絵画の淡い感じという印象を持ち過ぎているのではないかと感じました。オーケストラの曲を聴くと、そんな風には思えませんね。ところがピアノになると、そういう風になってしまって……。
- 井上:
- どうしても、こうあるべきだという、要は自分で価値観が決められないというところがあると思います。誰かが言ったからいいとか、みんなが言っているからOKだという、それを超えられないところがあるのでしょう。逆に言えば、そうやっておけば可もなく不可もなく、誰からも文句が来ないだろう、みたいなところを狙い過ぎているんですね。楽譜にはそう書いてないけれど素晴らしかった、というところを狙えない、そこまで到達できていないから、どうしても周りの意見にこだわってしまうのでしょう。
- 中島:
- そういうお話を作曲家の立場からしていただくと、とても説得力があります。今回井上先生が登場してくださったことは、とても意味がありましたし、そういう言葉を聞いて、受講者の皆さんも勇気をもらったのではないでしょうか。
ありがとうございました。
〈当日の講座内容〉
「時代様式に基づいたピアノ演奏とは─9」〜19世紀のピアノとピアノ音楽〜
講師:中島 裕紀

ピアノが楽器として完成され、古典派からロマン派を経て近代音楽に至るまでの全ての道のりを包括している19世紀は、ピアノに携わる私たちにとって、宝箱のような時代です。そこで生み出された音楽は、現代における私たちの演奏レパートリーの中心的な存在になっています。当時、最も新しく輝いていたピアノという楽器と、作曲家の取り組みについて、解き明かしながら、ピアノとピアノ音楽の魅力を探っていきたいと思います。
「子どものためのピアノ教本研究~ドイツ・オーストリアの教本を題材に~」
講師:浦川 玲子

普段目にする機会の少ないドイツ・オーストリアの子どものためのピアノ教本には、さまざまな個性やシリーズものがあります。その中から、我が国におけるピアノレッスンの現場にも導入しやすい教本を取り上げ、そのアイデアと内容を分析していきます。
「ドビュッシーのピアニズム」~現代音楽の始まり~
講師:井上 淳司

絵画の印象派の影響を受けたドビュッシー。西洋音楽史の「現代」の始まりにいるドビュッシーの音楽的な色彩感、芸術的な時間感覚を時代背景とともに探っていきたいと思います。いくつかのピアノ曲を読み解きながら「きれいな音楽」だけでは終わらないそのピアニズムの魅力や秘密からドビュッシーの本質に迫りたいと思います。