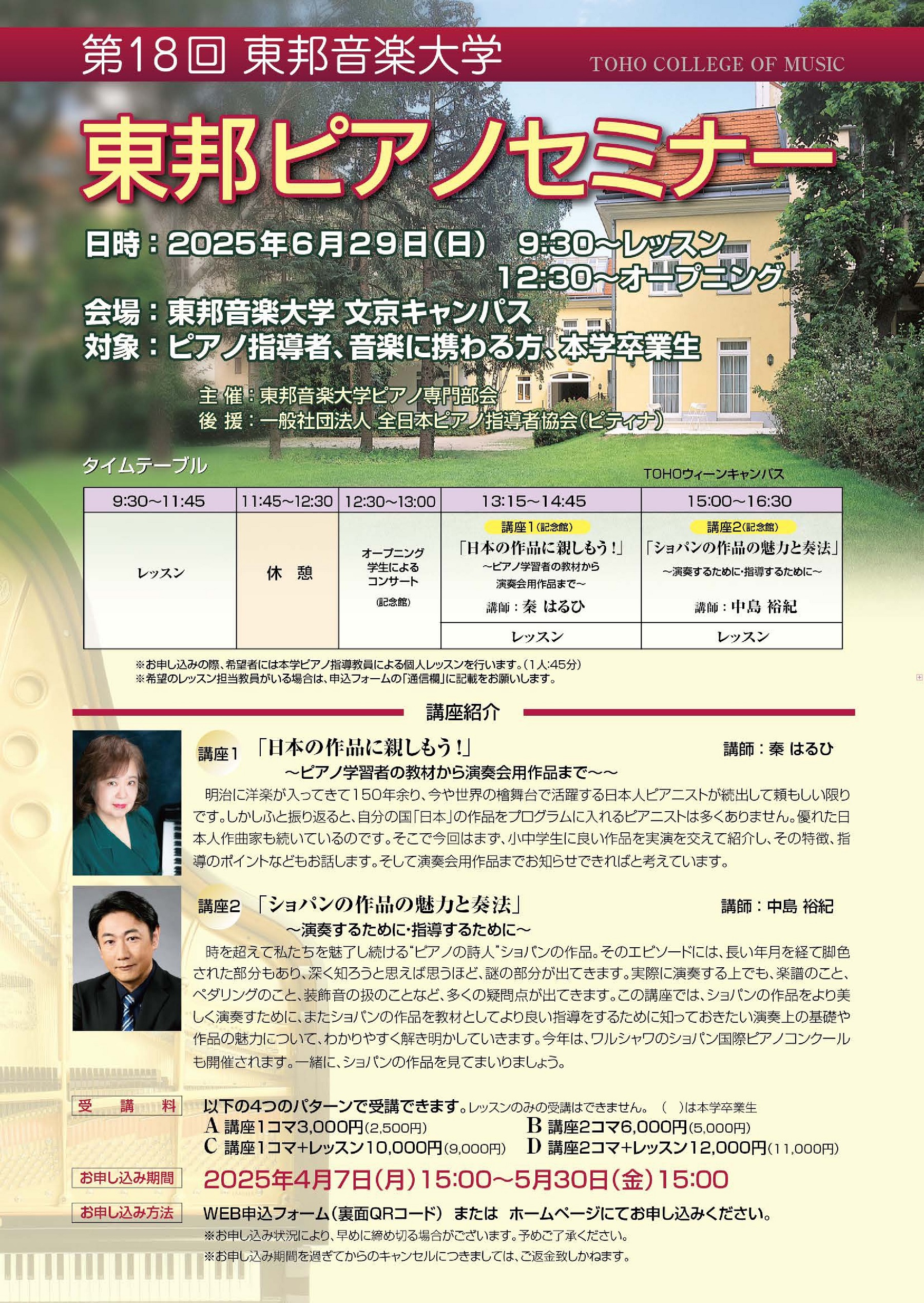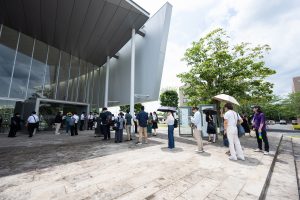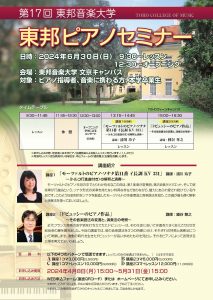記録的な猛暑もようやく過ぎ去り、秋の風が心地よく感じられるようになりました。
2024年10月5日・6日、芸術の秋を彩る「東邦ミュージック・フェスティバル」が川越キャンパスで開催され、地域の皆様、在学生のご家族・ご友人、卒業生・一般の皆様に大勢お越しいただき、両日とも大盛況となりました。
大学・短期大学・大学院のピアノを専門とする学生たちは、今年も2日間にわたり『煌めき!!ピアノコンサート』を開催しました。
このコンサートには、フェスティバルの2週間前に行われた出演者選考会にて選抜された18組・44名が出演し、2台ピアノを中心に、さまざまなピアノアンサンブルの名曲を披露しました。
今回のピアノダイアリーは、コンサートの曲目と出演者、当日の雰囲気を写真とともにご紹介します。
『煌めき!!ピアノコンサート at Studio B』 2024年10月5日 13:00~14:30
1日目は、川越キャンパス16号館3階にあるスタジオBにて開催しました。客席は常に満員で、熱気あふれる雰囲気の中で行われました。
♪ドビュッシー:『小組曲』より 1.小舟にて 3.メヌエット
海老原美子(短大1年) 堀田景子(短大1年)

社会人学生のお二人による、詩的で気品あふれる連弾でコンサートが幕を開けました。
♪W.A.モーツァルト(E.グリーグ編曲):ピアノソナタ ハ長調 KV545 第1、2楽章
甘 弦朋(大学3年) 大橋佳奈(大学4年)

良く知られたモーツァルトのソナタに、ノルウェーの作曲家グリーグによる第2ピアノパートが加えられ、美しくロマンティックな装いとなりました。
♪D.ミヨー:『スカラムーシュ』Op.165bより 3.ブラジルの女
宮本美咲(大学3年) 佐々木彩華(大学4年)

2台ピアノの代表的な名曲です。一転してラテン風の刺激的なリズムで活気あふれる雰囲気となりました。
♪A.ボロディン:歌劇『イーゴリ公』より ダッタン人の踊り
関口優香(大学4年) 坪井円香(大学4年)

ロシアの作曲家ボロディンによるオペラの名場面が、2台ピアノによる華麗な編曲で余すところなく表現されました。
♪三善 晃:2台ピアノのための組曲『唱歌の四季』 朧月夜 茶摘 紅葉 雪 夕焼小焼
浅野凜花(大学4年) 箱崎航平(大学4年)

誰もが知っている日本の唱歌とともに四季の移ろいが表現され、2台ピアノならではの美しい和声が会場を満たしました。
♪A.ローゼンブラット:カルメン・ファンタジー
重川美優(大学2年) 杉谷優太(大学3年)

この作品では、ビゼーの美しい旋律にローゼンブラッドがさらに情熱を注ぎこんでいます。二人の若き演奏者の強い鼓動とパワーが躍動しました。
♪P.デュカス:魔法使いの弟子
アンドリュース瑚彩(大学3年) 田中摩音(大学4年)

この作品はタイトルで示されるように様々な場面が去来します。軽快なスケルツォの拍子に乗って、オーケストラを思わせる色彩豊かな響きが展開されました。
♪M.ウィルバーグ:ビゼーの『カルメン』の主題による幻想曲
大井和奏 (大学2年) 日向野千鶴(大学2年) 工藤琴姫(大学2年) 鹿野陽菜(大学2年)

この日の最後の曲目は2台8手による演奏です。4人の奏者と2台のピアノによる大迫力のアレンジで、壮大にコンサートを締めくくりました。
一日目のコンサートは無事に終了し、演奏者、学生スタッフ、教員全員で記念撮影をしました。

東邦ミュージック・フェスティバルでは、学生たちが日頃の学びで得たことをのびのびと表現しています。
それは、演奏者のみならず、コンサートを運営するスタッフも同様です。

お越しいただいたお客様からは、学生スタッフへもたくさんの励ましとお褒めの言葉をいただきました。ありがとうございます。
『煌めき!!ピアノコンサート at Granz Saal』 10月6日 16:00~18:00
2日目のコンサートは、今年の東邦ミュージック・フェスティバルの最後を飾る演目として、グランツザールで行われました。
前日に引き続き多くのお客様が最後までお聴きくださいました。
この日の公演は音楽ホールでの開催であることに加えて、舞台上のセッティングも頻繁に変わります。
本学「地域連携・演奏センター」職員の方々のご指導のもと、学生スタッフも本格的なコンサート運営の体験を通じて多くのことを学ぶことができました。
♪W.ルトスワフスキ:パガニーニの主題による変奏曲
野口満理奈(大学4年) 吉田有沙(大学4年)

刺激的な不協和音やジャズ風のリズムを表情豊かに表現し、コンサートの幕開けに相応しい活気に満ちた演奏でした。
♪S.プロコフィエフ(M.プレトニョフ編曲):バレエ組曲『シンデレラ』より「シンデレラのワルツ」「ギャロップ」
改藤啓乃(大学4年) 松本佑希乃(大学4年)

プロコフィエフのバレエ音楽の2台ピアノ編曲です。現代的な不協和音をまといながら詩的でロマンティックな光景が目に浮かぶような演奏でした。
♪J.ブラームス:交響曲第2番 ニ長調 Op.73第1楽章
岩澤ことね(大学3年) 清原一龍(大学4年)

「ブラームスの田園交響曲」とも言われる作品です。Konzertfach(演奏専攻)のお二人による2台ピアノの演奏により、シンフォニックな響きが作り出されました。
♪M.ラヴェル:『スペイン狂詩曲』より 2.マラゲーニャ 4.祭り
宮本有紗(大学院2年) 新井あやの(大学院2年)

フランスの作曲家ラヴェルによる、スペイン情緒あふれる作品です。2台ピアノの可能性を極限まで広げたラヴェルの技法が、お二人の感性とともに華麗に繰り広げられました。
♪G.ホルスト:組曲『惑星』より 4.木星
斎藤愛実(大学院1年) 奥 光李(大学4年)

イギリスの作曲家ホルストの、おそらく最も有名な作品です。2台ピアノの迫力と、壮麗な中間部のメロディが印象的でした。
♪W.A.モーツァルト:ピアノ三重奏曲 ト長調 KV564 第1、3楽章
菅野爾音(ピアノ、大学4年) 岩本さくら(ヴァイオリン、大学院1年) 卢栀杨(チェロ、大学院1年)

今年の「煌めき!!ピアノコンサート」は、ピアノと弦楽器・管楽器による室内楽を3曲ラインナップしました。賛助出演の学生、研究員の皆さんも、心をこめて全力でこのコンサートに向けて準備してくれました。
モーツァルトのピアノ三重奏では、それぞれの楽器の個性とその調和が存分に表現されました。第3楽章の軽快さは、まさにモーツァルト作品の醍醐味です。
♪G.フォーレ:ピアノ四重奏曲第1番 ハ短調Op.15 第4楽章
今井風季(ピアノ、大学4年) 加賀竜太郎(ヴァイオリン、大学2年) 佐藤直樹(ヴィオラ、研究員) 井上伸一(チェロ、研究員)

ピアノ四重奏曲の傑作であり、非常な難曲でもあります。室内楽の経験豊かな4人によって、そのリズムと和声に生命が吹き込まれる熱演となりました。
♪L.v.ベートーヴェン:ピアノ五重奏曲 変ホ長調 Op.16 第1楽章
厚川もも(ピアノ、大学4年) 池田一翔(オーボエ、大学院1年) 落合 凜(クラリネット、大学2年) 内山紀佳(ファゴット、大学3年) 寺尾優那(ホルン、大学4年)

ピアノ五重奏は「煌めき!!ピアノコンサート」歴代最大の編成です。音色とアーティキュレーションが美しく調和し楽譜の隅々まで丁寧に表現された演奏で、この時代様式の魅力とベートーヴェン作品の奥深さが会場に満たされました。
演奏終了後は、舞台上セッティング変更の時間を利用して演奏者へのインタヴューも行いました。室内楽の演奏に対する熱い気持ちと、将来への夢を語っていただきました。

♪F.プーランク:シテール島への船出 C.ドビュッシー(レオン・ロケ編曲):アラベスク第1番
達崎桃恵(大学3年) 大坂一馬(大学3年)

再び2台ピアノによる演奏です。フランスの作曲家たちによる非常にピアニスティックな作品で、2台のピアノの音が2人の会話のように聴こえてきました。
♪M.ラヴェル:ラ・ヴァルス
遠藤乙彩(大学3年) 植松姫菜(大学3年)

今年のコンサートの最後を飾ったのは、Konzertfach(演奏専攻)のお二人による演奏です。2台ピアノという編成の魅力と大きな可能性を実感できる、圧巻の演奏で締めくくられました。
こうして今年の「煌めき!!ピアノコンサート」は無事に終了しました。
このコンサートに対する学生たちの意欲は年々高まっていると感じます。また、上級生がこの演奏会に向けて取り組む真摯な姿は後輩たちに素晴らしい刺激を与え、学生たち全員の成長につながっているのは間違いありません。
そして、今年も連日多くのお客様にお聴きいただいたことで、学生たちのピアノへの情熱と一人ひとりの成長は一層確かなものとなりました。この場を借りて心よりお礼申し上げます。
来年度もこのコンサートを続けてまいります。ぜひまた会場にて学生たちを応援してくださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。