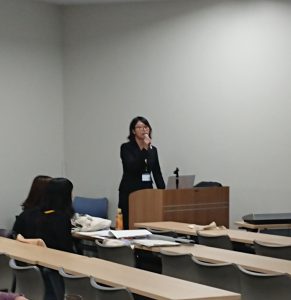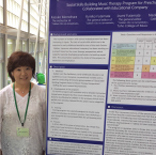日本音楽心理学音楽療法懇話会に学生たちが参加しました
タイトル:日本音楽心理学音楽療法懇話会に学生たちが参加しました
現在、感染症対策として、音楽療法の勉強会などはオンラインで行われることが多々あります。2020年7月8日に「日本音楽心理学音楽療法懇話会」のシンポジウムがありましたが、これもオンラインで開催されました。
本学の音楽療法専攻の学生たちもたくさん参加しましたが、その中で3年生の鎌倉萌菜穂さんが参加した感想を書いてくれました。
「今回、初めてオンラインで日本音楽心理学音楽療法懇話会に参加しました。シンポジウムのテーマに沿って感想を書いていきたいと思います。
まず、『音楽療法がわからない』では、3名の先生方の話題提供を聞いて、私もテーマのような気持ちを持ったことがあることを思い出しました。もしかしたら、この気持ちは音楽療法を学ぶ者が皆通る道なのではないかと思います。しかし、音楽療法に足を踏み入れたばかりの私たち学生の思う「音楽療法がわからない」と、実際に様々な経験をされ、研究をされてきた先生方が仰る「音楽療法がわからない」は、質の違うものであると感じました。音楽療法はわからないものだからこそ、学び続けて研究していくことが必然的で重要なのかもしれません。
次に、今の社会に関連した『コロナ共生時代の音楽療法』というテーマで参加者も含めた討議をしました。私もこのご時世でどのように音楽療法を実施しているのか気になっていたので、オンラインでのセッション、野外でのセッションの実施等、どれも興味深いお話でした。私は、コロナの影響で音楽療法の形態に変化が生じることは、基本対面式で行う音楽療法には悪影響ばかりだと思っていましたが、音楽療法の多面性を知ってもらう機会になる等の良い影響もあったことに驚きました。これを機に、音楽療法の持つ様々な形態を知ってもらえるきっかけになればいいと思うと同時に、これこそが音楽療法の利点だということを学びました。
オンラインは、大学の授業以外で使ったことがありませんでしたが、今回オンラインで参加してみて「地方からの参加が気軽にできる点」「時間やそれぞれの状況に合わせて参加ができる点」「同時作業が行えて効率よく進められる点」という3つのメリットを感じました。今後もこのような形が社会で増えていくのかなと思いました。
今回懇話会に参加してみて、音楽療法の幅広さを改めて実感しました。今後どうなるかわからないコロナ共生時代にも対応できるように、新たな発想も大切にしつつ、残り半分ほどの学生生活に励んでいきたいと思います。 」
(音楽療法専攻 3年 鎌倉萌菜穂)
コロナ禍でも、学生たちは着実に学びを進めています。困難な状況でも、工夫したり想像力を働かせたりすることの大切さを、日々実感しています。
音楽療法専攻チームリーダー 准教授
木下 容子